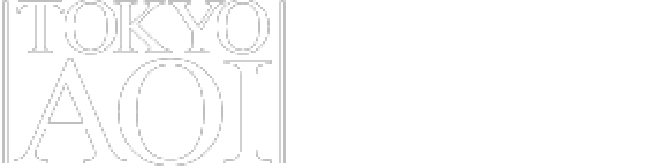TOPICS
トピックス
「企業価値担保権」についてざっくり解説
1.企業価値担保権とは
「企業価値担保権」とは、債務者の企業価値全体を担保に取るという新しい担保制度です。
2024年3月15日付で「企業価値担保権」等の新制度を含む「事業性融資の推進等に関する法律案」が閣議決定され、同年5月21日に衆議院通過後、同年6月7日に参議院で可決されました。事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」といいます。)は2026年5月25日に施行されます。
2.制定に至った背景
従来、金融機関等が会社に対し融資をしようとする場合、債務者による返済の実効性確保のため「ヒト」、「モノ」を担保に取るということが行われてきました。「ヒト」に代表されるのは連帯保証人等であり、「モノ」に代表されるのは、不動産への抵当権設定等です。近年、動産や不動産等の有形資産を担保とする場合の担保価値の評価基準や評価方法はある程度確立されていますが、無形資産(いわゆる人的資本、営業ノウハウ、知的財産権、顧客基盤等)を担保とする場合の担保価値の評価基準や評価方法は未だ確立されているとはいえません。そのため、特に無形資産を多く保有する企業に対して積極的な融資を実行しにくいといった問題点のほか、債務者の不動産等に担保権を有する債権者においては債務者の事業そのものに対して無関心(あるいは関心が薄い)であり、経営改善に向けた指導・助言等の適時・適切な実施が遅れるといった問題点が指摘されていました。企業の事業性を評価し、その事業全体に対して担保を設定することができれば、債権者の積極的な融資の促進につながることに加え、必然的に債務者の事業に対する債権者の関心が高まり、経営改善施策の実施・助言が期待できるようになります。こうした企業の“事業性”を評価した融資の需要に応える形で設計されたのが「企業価値担保権」です。
3.企業価値担保権の目的財産
企業価値担保権の担保目的財産は、債務者の「総財産」となります(法第7条第1項)。したがって、この「総財産」には、将来において債務者が有することとなる財産や、営業秘密、技術上の秘密等の事業上の利益、労働契約や商取引に関する契約の契約上の地位、将来キャッシュフローや“のれん”も対象になります。なお、似たような概念としてLBO(=Leveraged Buyout)やプロジェクトファイナンスにおいて利用される「全資産担保」がありますが、これは債務者の有する有形資産の全てについて、“個別に担保権が設定”されるものですので、その点で企業価値担保権とは区別されます。
企業価値担保権の担保目的財産は、債務者の通常の事業活動の範囲内である限り、債務者が自由に使用、収益及び処分することが認められています(法第20条第1項)。一方、重要な財産の処分、事業の全部又は重要な一部の譲渡等その他の通常の事業活動の範囲を超える取引は、企業価値担保権者の同意を得る必要があり(法第20条第2項)、同意を得ずに行った取引は原則として無効となりますが、善意無重過失の第三者には対抗できません(法第20条第3項)。
4.企業価値担保権の設定方法
債務者(設定者)は会社法上の株式会社及び持分会社に限定されています(法第2条第2項)。また、被担保債権者は限定されていないため、金融機関だけではなく再生ファンド等も被担保債権者となることができますが、企業価値担保権の設定は所謂セキュリティ・トラストの仕組みを用いなければなりません。すなわち、債務者を委託者、金融庁の免許を受けた企業価値担保権信託会社(企業価値担保権者)を受託者、被担保債権者を受益者として、企業価値担保権の管理・行使を目的とした信託を設定する必要があります(法第8条)。その主な理由としては、担保権者に業規制を及ぼすことにより、債務者の事業に不当な影響を及ぼす目的で企業価値担保権が取得されることを回避する点にあるとされています。
企業価値担保権は、債務者の商業登記簿にその登記をしなければ効力が生じないものとされています(法第15条)。また、他の質権や抵当権等との優先順位は、それらの担保権に係る対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の先後によるものとされています(法第18条)。
5.企業価値担保権の実行フロー
企業価値担保権の実行フローは、まず、企業価値担保権者たる受託会社が企業価値担保権実行手続開始の申立てを行い、裁判所が実行手続開始を決定した後、管財人による事業経営と事業譲渡が行われ、特定担保権者は当該譲渡代金から配当を受けるという流れです。以下、順に見ていきます。
(1)企業価値担保権実行手続開始の申立て
被担保債権について債務不履行があった場合、受託会社は、全ての被担保債権者の指図を受け、企業価値担保権実行手続開始の申立てを行います(法第83条第1項、第61条)。
(2)企業価値担保権実行手続開始決定
裁判所により企業価値担保権実行手続開始決定(法第87条)がなされると、管財人が選任され(法第88条第1項)、通常の債権については弁済が禁止されます(法第93条第1項)。
もっとも、企業価値担保権の価値を維持するためには、事業継続に必要な商取引債権や労働債権等を随時弁済することが必要となるため、そういった債権については被担保債権に優先して随時弁済される制度となっています(法第93条第2項、第129条)。
(3)担保目的財産の管理と換価
実行手続開始決定後、管財人は、裁判所の監督の下、債務者の事業経営や担保目的財産の管理を行うとともに(法第113条、第114条)、裁判所の許可を得て、スポンサーへの事業譲渡(法第157条第1項)又は個別処分(同条第2項)の方法により担保目的財産の換価を行います。
なお、債務者が有する許認可等に関しても、事業譲渡に際して管財人が譲受人に承継させることの許可を申し立てることが可能です(法第159条)。
(4)配当手続き
管財人は、企業価値担保権の目的財産となる事業の譲渡が完了した後は、被担保債権に対する配当を実施します(法第166条)。かかる配当は、事業譲渡に基づいて得られた譲渡代金等から、共益債権や弁済禁止の例外として随時弁済の対象となった債権に対する弁済原資を取り置いた残額を原資として行われます。
6.金融機関等にとってのメリット・デメリット
(1)メリット
高い技術力・ノウハウやビジネスモデルを有するにもかかわらず、引当てとなる有形資産を有しないが故に従前は融資を躊躇せざるを得なかったスタートアップ企業等に対する融資が行い易くなると考えられます。
(2)デメリット(課題)
無形資産や事業性の評価そのものを適切に行うことができなければ、過大に担保価値を評価してしまう危険があり、場合によっては貸倒れによる善管注意義務違反のリスクがあります。そのため、企業価値担保権の設定を受ける金融機関等は、技術力・ノウハウやビジネスモデルといった無形資産を含む債務者の事業価値についての評価を適切に行う能力(そのような評価を行うことができる人材の育成・確保)が必要になります。
本TOPICSの執筆者:西野築、市川雷
※2025年8月31日時点の情報に基づく記事です(参考にされる場合は新法の施行や関連法令の改正等がないかを必ずご確認下さい)。