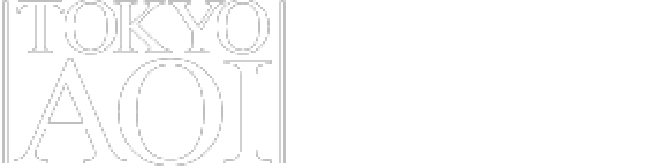TOPICS
トピックス
M&A実施時に問題となり得る「経営者保証」について解説
1.中小企業のM&A後における経営者保証の解除
最近、中小企業のM&A後において、買主が売主の「経営者保証」を解除しないことでトラブルとなるケースが散見されます。中小企業が金融機関から融資を受ける際、社長が連帯保証人となるケースがありますが、会社売却後、社長(売主)が経営に関与しなくなったにもかかわらず、その後買主によって金融機関に対する経営者保証解除のための対応がなされないといったものです(なお、金融機関としては、M&Aによって代表者が変更される場合、経営者保証を解除または変更するのが一般的な運用です。)。
しかし、なぜこのような事態が生じるのでしょうか。
2.問題の発端(?)と背景
この問題の背景には、ある事件が関係していると考えられます。朝日新聞デジタルの連載「M&A仲介の罠」(全6回)では、A社に関する事例が取り上げられていました。問題となるA社は非上場企業であり、2021年頃から約30社のM&Aを実施しましたが、2024年中旬までに買収した企業のうち約10社が倒産、5社が営業停止となりました。その中で、経営者Xは自身の会社B社をA社に売却した後も、B社が負っている債務の返済に苦しんでいることも記されていました。
A社はM&Aによって買収したB社の資産を毀損し、経営者保証を解除しないことで、経営者XにB社の主債務の返済を強いる構図をとっていたようです。このような事例では、売却後の経営者がM&A仲介会社に対して訴訟を提起しているものも散見されます。
3.経営者保証が解除されない理由
経営者保証が解除されない理由として、以下の3点が挙げられます。
(1)株式譲渡契約書に経営者保証の解除規定がない
(2)同契約書に経営者保証の解除について記載があるものの、買主の努力義務として規定されているに止まる
(3)同契約書に経営者保証の解除が法的義務として規定されているものの、実効性のある担保手段がない(買主が無資力である等)
(1)と(2)の場合、弁護士やM&A仲介会社が株式譲渡契約書に明記する等の適切な対応をとることで一応は回避可能と考えられますが、(3)の場合、買主に対して経営者保証の解除義務違反を理由とする損害賠償請求を行っても、買主が無資力だと実効性がないこととなります。そのため、株式譲渡契約書には、買主は譲渡実行日以後、速やかに経営者保証を解除する旨定めるだけでなく、買主が経営者保証を解除するまで、譲渡代金の支払の一部を留保することにより買主の義務不履行を抑止する等、買主による保証解除のための実効性のある措置を定める必要があると考えます。
4.最近見聞きした事例
最近では、M&A実施後の一定期間のみ経営者保証を存続させるケースも耳にします。例えば、「M&A実施後も6ヶ月間は従前と変わらず職務に従事すること」を条件とし、「当該条件成就後に経営者保証を解除する」といった規定です。これは、M&A後のPMI(Post-Merger Integration)の実効性を担保するために買主側が求めているものと考えられます。
もっとも、経営者保証の存続を一定期間に限定する場合でも、買主の対応次第では売主が連帯保証人として経済的リスクを負う可能性があるため、慎重な対応が求められます。売主側の弁護士は、場合によっては取引中止(Deal Break)を覚悟してでも買主やM&A仲介会社と交渉すべきだと考えます。
5.経営者保証にまつわるルール等
経営者保証については、2013年12月公表の「経営者保証に関するガイドライン」や、2019年公表の「経営者保証に関するガイドラインの特則」が存在します。さらに、2020年4月からは、経営者保証に代わる新たな信用保証制度として「事業承継特別保証制度」が開始されるなど、制度の整備が進んでいるほか、関連するルールについては以下のとおりです。
| 関連するルール等 | 概要 |
| 中小M&Aガイドライン(第3版) | 事前相談の推奨 |
| M&A支援機関協会 広告・営業規程第12条の2、附則3 | 取引実行日から2か月以内の解除義務 |
| 一般社団法人M&A仲介協会 「特定事業者リスト」 | 取引実行日から一定期間未解除(※)だった事業者を「特定事業者」として登録 |
(※)2025年4月21日時点では、取引実行日から60営業日とされています。
「特定事業者リスト」はあまり聞き慣れないかもしれませんが、これは2024年10月から運用が開始された比較的新しいものとなります。取引実行日以降の一定期間、経営者保証を解除しない等の不適切な行為を行った買主の情報をM&A仲介協会(以下「協会」といいます。)内の会員間で情報共有するものです。今後、中小企業のM&A実務に関与する弁護士は、このリストの存在を常に意識する必要があります。例えば、一度リストに登録されてしまうと、今後のM&A戦略に対して予想外の不利益が生じるリスクがあります(M&A仲介会社に、リスト登録されていることを理由に経営者保証のあるM&A案件の紹介を受けられなくなる等の事実上の不利益を被ることが予想されます)。リスト登録は協会の会員が関与していなくても、協会への情報提供等でも行われます。
上記売主の不利益に鑑みると、今後、未解除期間が短縮される可能性もあることから、中小企業のM&Aに携わる弁護士としてどのように対応するのがより良いDealとなるのか、今後の動向に注目して参りたいと思います。
本TOPICの執筆者:市川雷
※2024年5月8日時点の情報に基づく記事です(参考にされる場合は新法の施行や関連法令の改正等がないかをご確認下さい。